- ホーム
- コラム
- 沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム
- アロマオイル
沙羅 Sara の「ほっと一息」コラム

体質改善のアロマオイルを作る〜ナード・アロマインストラクターコース〜
2017/10/27
ナード・ジャパン インストラクターコースLesson3(1)〜精油の芳香性分類の基本〜
2017/08/25
昨日の、ナードジャパン認定校メディカアロマでのインストラクターコースの講義は、まるで化学の授業でした。
遠い昔に「化学 I」をひたすら頑張った(「化学II」の名目で「化学I」を学ばされたような…)文系生徒としては、なかなか手強い。
「精油に含まれる芳香分子は、炭化水素か、炭化水素の骨組みに官能基の付いた分子」と言われても…、「官能基」につまずくわけです。
官能基とは「有機化合物の分子内に存在し、化合物の特徴的な反応性の原因となるような原子又は原子団」ということですが、…すでに「官能基」という用語に、居心地の悪さを感じたりします。
…そもそも「用語」が落ち着いて私の中に入ってこない…というのを実感します。
「炭化水素か、炭水化物の骨組み」=「骨格」に3つあって「テルペン系」(=イソプレン骨格)「芳香族」(=ベンゼン環骨格)「脂肪族」(=鎖状骨格)。こちらを横軸に取ります。
(イソプレンはC5H12の分子式を持つもので、通常は単独で存在せず、2つ以上が結合して存在しているそうです。)
縦軸は「官能基」で、「官能基なし」から始まり、「水酸基−OH」「アルデヒド基−COH」「ケトン基−CO−」「カルボキシ基−COOH」「エーテル結合−O−」「エステル結合−COO–」と並びます。
これを組み合わせる訳です。
たとえば、テルペン系の「官能基なし」は「モノテルペン炭化水素類」と「セスキテルペン炭化水素類」の2つ。テルペン系の「水酸基」は「モノテルペンアルコール類」と「セスキテルペンアルコール類」と「ジテルペンアルコール類」の3つとなります。
モノ、ジ、トリ、テトラ…は1、2、3、4、だったと思うのですが、セスキって?と思いました。
(ラテン語と思い込んでいたのですが、ギリシャ語でした…。)
セスキは1.5なんだそうで、イソプレンは通常は単体では存在しないので、イソプレンが2つのテルペンをモノテルペン、3つのテルペンをセスキテルペン、4つのテルペンをジテルペンと言うそうです。
…疲れますよね。この辺でやめます。
まあ、そんな化学の授業の中にも、楽しい実習があって、昨日は「ローズの香りのボディミスト(ローション)を作りました。
・バスオイル(乳化剤)…10滴
・ローズ精油……………… 1滴
・ローズウォーター………50ml
ローズはホント高価で、1滴で260円! でも、とんでもなくいい香りに包まれます。
ローズ精油を生成するときに生まれるのが「ローズウォーター」で、その二つを組み合わせると、本来の「バラ」の香りに近いものが生まれます。
(アプリコット油で1%に希釈した「プレミアム ローズ」もありますが、それでも10mlが7800円もします。)
今日から入院する母に持たせようかな、と思います。
画像の一番左のボトルに、今回作ったボディミストが入っています。
ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(2)〜植物から精油を取る方法〜
2017/08/19
ナード・ジャパン インストラクターコースLesson2(1)
2017/07/28
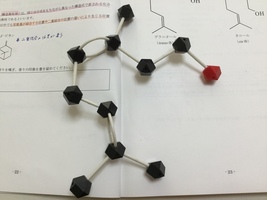
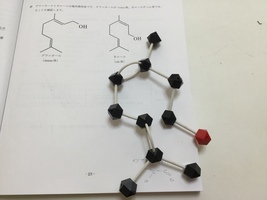
赤で表したOH基の付いている向きが違いますよね。
ナード・ジャパン インストラクターコースLesson1(3)
2017/07/19
-
 読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
読むカウンセリング
ん、なんだか、変だぞ…と、不調への入り口に気づくとき。あるいは、もう既に調子が悪くなっているときに。読んで少し
-
 大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜
折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、
大事はこれをみずから決す〜「折々のことば」鷲田清一 #3104〜
折々のことば。2024年6月2日の鶴見俊輔の言葉。小事はこれを他にはかり、大事はこれをみずから決すというのが、
-
 いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜
折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド
いつか思い出に〜「折々のことば」鷲田清一 #3091〜
折々のことば。2024年5月20日のシドニー・スミスの言葉。「このことも、いつか思い出にできるかな」 シド
-
 放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち
「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語
放ったらかしのグレーゾーンの子どもたち
「発達障害」という言葉が、割と頻繁に話題にされるようになりました。この言葉自体は1963年にアメリカで法律用語
-
 復活の翌日
ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸
復活の翌日
ちょっと体調がよろしくなくて。あれよあれよという間に、7月末からカウンセリングのお仕事もお休みしてしまって。丸
カウンセリングルーム 沙羅Sara
 あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
あなたはあなたのままで大丈夫。ひとりで悩みを抱え込まないで。
明けない夜はありません。
電話番号:090-7594-0428
所在地 : 生駒市元町2-4-20
営業時間:10:00〜19:00
定休日 :不定休






















